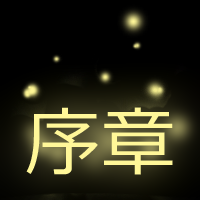■第8回例大祭 七曜様 新刊『光』

――幻想郷のとある夜更け。
――二人きりの森の中。
「はははっ! どうだ霊夢、驚いたろ!?」
「あははは……はぁ……う、うん。びっくりした。今日のあんたには負けたわ……まさか本当にとっておきがーー」
――魔理沙の初めての魔法。
――霊夢の初めて見る顔。
――それが嬉しいだけなのに。
「何故、今、本気を出した? お前が全力を出せば、魔理沙が歯も立たないことくらいは分かっているだろう!!?」
――いつも差をつけられる彼女。
――努力して追いついたと思っても、彼女は遥か先にいて。
「私が見ても訳がわからんヤツにも勝っちゃう霊夢の実力の方が、訳がわからん。あいつのことはずっと見てきたのに、な」
――それでも、彼女のことを諦めきれない。
「とっておきが、あるんだ」
「また、そんな嘘つかなくていいわよ」
「嘘じゃないさ」
「じゃあ、見せてもらおうじゃないの」
――手を伸ばしても、届くことのない月ならば、せめて流星の光を。
∗
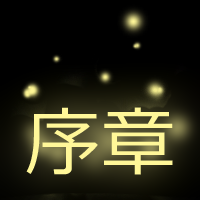
森の中を走る少女が二人。
駆け足に伴って、手に持ったカンテラが忙しなく揺れている。後ろを行く少女の眼にはしゃぎ回る明かりが映る。
「そんなに揺らして火が消えたりしないの?」
「大丈夫さ! これ、魅魔様の部屋から無断で借りてきた魔法のカンテラなんだ。ほら!」
元気の良い掛け声と共に右手を力の限り振り回した。鉄の擦れる騒がしい音が森に響く。
まるでカンテラが返事をしているみたいだ。心なしか明かりも強くなったように見える。
人里から少しばかり離れれば緑豊かで自然の摂理に従順な世界である。
それは決して穏やかなだけではなく、弱肉強食という言葉も当てはまることも意味している。
人里離れた場所に住んでいた年端もいかぬ彼女たちも、もちろんその理をわかっていた。
それでもなお、先を行く少女は宵闇の中にあって太陽のような笑顔を浮かべてもう一人の少女の手を引いている。
前を見る、猫のような大きい瞳には、揺れるカンテラの放つ光がきらきらと反射して、あたかも輝いているようだった。
おおよそ人がよく通っているとは言い難い、ろくに踏み場もない森の中は、カンテラの明かりだけでは心もとない。
それにも関わらず道が見えているかのような迷いのない足取りで進む。
導く先には、大人の半分ほどの背丈しかない少女たちが駆け回るには、十分過ぎるほどの開けた森の一角があった。
「はぁ……はぁ……着いたぜ、ここだ!」
満面の笑みを浮かべたまま、夜に溶け込む黒のワンピースに包まれた肩を大きく上下させながら少女は呼吸する。
「もう……こんなとこに何があるのよ」
続く少女は巫女装束の袖で額の汗を拭いつつ問いかけた。
「何があると思う?」
走ったお陰で頭から落ちそうになっていた帽子を被り直ながら、質問を質問で返した。
服と同色の、三六○度を覆う大きな鍔のついた三角帽子は、着衣と相まって魔女を絵に描いたような姿だった。
「何にもないと思う。もしくは木しかない」
憮然とした表情で即答する巫女装束の少女。
「霊夢……ちゃんと見ろよ。あれが木に見えるか?」
言いながら指を差した先に、古ぼけた桶が置かれていた。
疑問があるとすれば、なぜ桶が人気のない森の中に置かれているかということだけだろう。
だが、案内人が連れてきた場所において、明らかに不自然な存在を自ら指摘する時点で、それは彼女が設置した物で
あることの裏付けにしかならなかった。見え透いた解など謎でも不思議でもない。
霊夢の体を脱力感が襲う。
「どうせ魔理沙が置いたんでしょ、あれ。別にすごくもなんともないじゃない」
すごいものを見せてやる、と言われて半ば強制的に連れてこられた場所に彼女が置いた桶が一個あっても何も驚く
ことはない。そんな霊夢のつまらなそうな言葉に、魔理沙と呼ばれた少女は得意気に答えた。
「そりゃそうだ。すごいのは桶じゃない。桶の中身さ」
小走りで桶に近寄っていく魔理沙の後を霊夢がのんびりと追う。先に桶の元へ辿りついた魔理沙はカンテラを地面に
置いて、霊夢に見られないよう注意しながら胸のポケットからくしゃくしゃになったメモ紙を広げて、内容を確認した。
霊夢をこれから驚かせてやれると考えると、魔理沙はわくわくと踊る胸の高鳴りを抑えられなくなりそうだった。
その一方で、まだ覚えたての上に初めて一人で挑戦することに不安も感じている為か、形の整っていない汚い字がうまく
読みとれなかった。自分で書いたものながら、字の下手くそさに辟易する。
解読に焦っていると、霊夢の足音が近づいてきた。
――熟成キノコの粉、二掴み以上入れない、混ぜる。
言葉の断片を拾い読みしてから急いでメモ紙を元の場所に押し込んだ時、霊夢が隣に並んだ。
見栄を張って連れてきた手前、今さら最終確認をしていたとなれば格好がつかない。魔理沙の喉から何かを飲み込む
音がする。恐る恐る横目で霊夢の様子を伺うと、彼女の視線は桶の中に注がれていた。
「何この、桶に詰まってる砂みたいなの」
霊夢が桶を覗き込んだまま言う。
桶には明らかに自然では見かけないであろう、派手な色をしたカラフルな砂がこれでもかという程に詰まっていた。
ひとまず自尊心は保たれたことに魔理沙は胸を撫で下ろし、その質問を待ってましたとばかりににやりと笑って霊夢の
横顔を覗きこんだ。
「何だと思うー?」
「変な色の砂」
表情も変えず色気のない返答をする霊夢に、魔理沙の顔に落胆の色が滲む。
「お前、もうちょっと別の感想ないのかよ……」
「ない」
二度に続くきっぱりとした霊夢の言葉に、今度は肩を落として溜息をつく魔理沙。このまま終わらせたのでは
ここまで彼女を連れてきた意味は無い。失敗は許されないんだ! と、魔理沙はうなだれていた顔を上げ、
肩をいからせて鼻息を荒く噴き出した。
大体、本番はここからなのだ。ここで驚いてもらう必要はほとんどない。普段は見かけない色の砂だからと
霊夢の反応にちょっぴり期待してはいたが。
魔理沙は仕切り直す為に、厳めしく咳払いをした。
「ゥオッホン。ここまで来たのは他でもない。まだ誰にも見せてないとっておきを披露してやるためさ。
これからあっと驚く魔法を見せてやるぜ!」
霊夢を指差しつつ、凛とした表情で言い放つ魔理沙。しかし言葉を向けられた霊夢は、
触れそうな距離にある人差し指にも気を留めず、魔理沙が遠いところにいるかのような目をしただけだった。
「反応!!」
「……へぇー」
あまりの無反応に思わず大声を出してしまう魔理沙。それにさえ、霊夢は肺の空気が漏れた程度の声しか出さなかった。
「うぐっ……とっ、とにかく見てろよ!」
若干の涙目になりつつ、魔理沙がメモ紙をしまったところとは違うポケットから袋を取り出す。
その中に手を突っ込んでひと掴みの黒い粉を桶の中にばら撒く。
――ちょっと足りないかな。
いまいち自信が持てず、もう一度袋に手を突っ込んで少しだけ粉を追加してみた。
さっきのメモ書きの一端が頭の中で復唱されるが、まだ一掴み半だから大丈夫だろう。
魔理沙はひとつ頷き、桶の下に隠してあったすり棒のようなものを取り出して、びしっと霊夢に向ける。
いちいち人のことを差すな、と言葉が出そうになったが、霊夢は堪えておいた。
「ほんっっとうにすごいんだからな!」
「早くやりなさいよ」
期待もへったくれもない霊夢の言葉に魔理沙は頬を膨らませる。
「見てろよ! 本当に驚くんだからな!」
大声を出しながら手に持っていた棒を桶へと突き立てる。砂利が擦れ合う乾いた音が何度も鳴った。
桶の中身がこれからどうなるのかと、霊夢は魔理沙の横へと移動して様子を観察する。
音の数が十を超えたところで、桶に詰まった砂の隙間から、光が漏れた。
「よし! 行けぇ!」
小さく、焚火の薪が弾けるような音がした。一拍置いて桶の中から光球が飛び出すのを、二人は反射的に眼で追い掛ける。
筆を勢いよく走らせるかの如く、光球は鮮明な黄色い光の尾を引いて空へと上がっていく。
やがて上昇する力を失い、空中で止まった。二人の視線が注がれる。
魔理沙が小さく「行けっ……!」と呟いた、次の瞬間。
光球が心地よい炸裂音と、輝く飛沫を散らした。
一度に数えきれないほど分裂して、大小様々の光を降らせた。魔理沙は抑えきれない笑顔を浮かべながら霊夢の顔を見る。
小さく口を開けて、彼女も光に見入っていた。
「……おー。花火だ」
本物には似ても似つかないけど。と続ける霊夢の声を遮って、魔理沙が声を上げる。
「やった、成功だっ! どんどん行くぜ!」
魔理沙の手に俄然力が籠もる。次々に上がる光球の様々な色は、空へ向かって真っすぐな虹を描き出す。
高く上がっていっては空のキャンバスに光の絵具を振りまいて、七色の光の幕を生んだ。
空の星が舞い降りて来る。
緩やかに揺らめきながら落ちてきた光は、大地に辿りついても輝きを失わずに暗闇を彩った。
► 本文 黒麻呂<七曜>
► 挿絵 yange<三草五里>
► 『光』 全106P \500
► 原作 上海アリス幻楽団
► 第8回 博麗神社例大祭 け−25b にて頒布